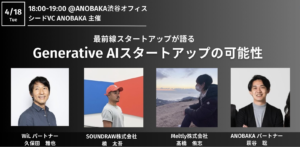皆さん、こんにちは!ANOBAKAの川野です!
前回から「Generative AI Conference Tokyo」にて実施したセッションの内容についてお届けしていますが、2本目となる今回はAIを活用して急成長中のスタートアップとして、株式会社Sales Marker 代表取締役CEO 小笠原 羽恭氏・株式会社PeopleX 代表取締役CEO 橘 大地氏にご登壇いただいたセッションの内容についてお届けしていきます!
=================
【登壇者】
◾️小笠原 羽恭氏
新卒で野村総合研究所に入社し、新規事業開発に従事。その後、戦略コンサルティングファームにて、営業変革・DX推進プロジェクトを多数リード。2021年に株式会社Sales Markerを創業。国内初の「インテントセールス」を実現するソリューション『Sales Marker』を開発・提供。2025年には、マルチ AIエージェント『Orcha(オルカ)』をリリース。営業に限らず、企画、マーケティング、人事、経営など多様な職種の業務で、意思決定・資料作成・タスク実行・記録管理をAIが一気通貫で支援することで、生産性と成果を飛躍的に高める革新をもたらしている。2023年「Forbes 30 Under 30 Asia List」選出。一般社団法人生成AI活用普及協会協議員。著書に『AIエージェント時代の成長戦略『インテントセールス』 – 組織の成果を最大化するための革新的アプローチ』がある。
◾️橘 大地氏
株式会社PeopleX 代表取締役CEO。2010年東京大学法科大学院卒業。弁護士資格取得後、株式会社サイバーエージェント、GVA法律事務所にて、弁護士として企業法務活動に従事。2015年に弁護士ドットコム株式会社に入社し、クラウド契約サービス「クラウドサイン」の事業責任者に就任。2018年4月より同社執行役員に就任、2019年6月より取締役に就任。2024年4月株式会社PeopleXを創業し、エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の運営の他、対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を開発。2024年10月「エンプロイーサクセス 社員が成功するための7つの指針」発刊。2025年5月「AIによる採⽤⾯接・⼈事評価サービス協議会(略称:AIAC)」を設立し、代表理事に就任。
【モデレーター】
◾️小林晃
千葉県習志野市出身。東北大学工学部航空宇宙工学科を卒業し、新卒で双日株式会社に入社。自動車本部にて東南アジアを中心とした事業会社管理・新規事業開発に従事。2023年2月よりANOBAKAに参画し、投資担当として新規投資先開拓や既存投資先支援に従事。
テーマ1:生成AI黎明期の試行錯誤:早すぎた挑戦と学び
小林:生成AIの大きな変化といえば2022年のChatGPTの登場で、2023年以降に盛り上がってきたように思いますが、これまでの約2年における「AI活用がうまくいった/いかなかった」の変遷を教えてください。
小笠原さん:Sales Markerとして2023年に「AIセールス」の機能を出したのですが、当時はアメリカでも前例が見つからず、日本においてもアメリカにおいても初だったと思います。をGPTのようなチャット画面上で商談獲得まで完結させる構想だったのですが、時期尚早で市場には浸透せず、当時の挑戦としては失敗でした。
既存プロダクトに埋め込む形で展開しており、プロダクト内に新しく「AIセールス」というタブを設け、AIに頼めばSales Markerの各機能を対話型で利用できる設計でした。ただ、クライアント様からは仕組みがなかなか理解されにくく、ブラックボックス化してしまい、結果的には従来のSaaSインターフェースの方が受け入れられました。
小林:「早すぎた」というのは、今振り返ると具体的にどういった点でしょうか?
小笠原さん:当時はまだ多くの方にとって、“生成AI=テキストが返ってくる”程度のイメージしか持たれていませんでした。実際は、ターゲットリスト作成からインテントでの絞り込み、文面生成、アプローチ、商談獲得までを一気通貫で自動化するものでしたが、その全体像をユーザー様にきちんとイメージしていただけていませんでした。今でこそ、AIで可能なことのイメージは広く浸透していますが、当時はそこまで啓蒙が進んでいないことを十分に理解できていなかったと思います。
橘さん:世の中で一番多い失敗は「とりあえず全社でChatGPTを使えるようにしたものの、何も起きなかった」というパターンでしょう。これは社会的損失だと思います。そしてもう一つ、昨年から今年にかけて起きているのが「自社開発のAIエージェントをPoCで救ったものの、何も起きなかった」というパターンです。これは今年のトレンドにもなっていると思います。
そもそもスタートアップ側と大企業側ではエコノミーがまったく違います。スタートアップの世界では、Cursorのような開発系ツールが最も速く業務フローから切り離せないレベルにまで浸透していました。
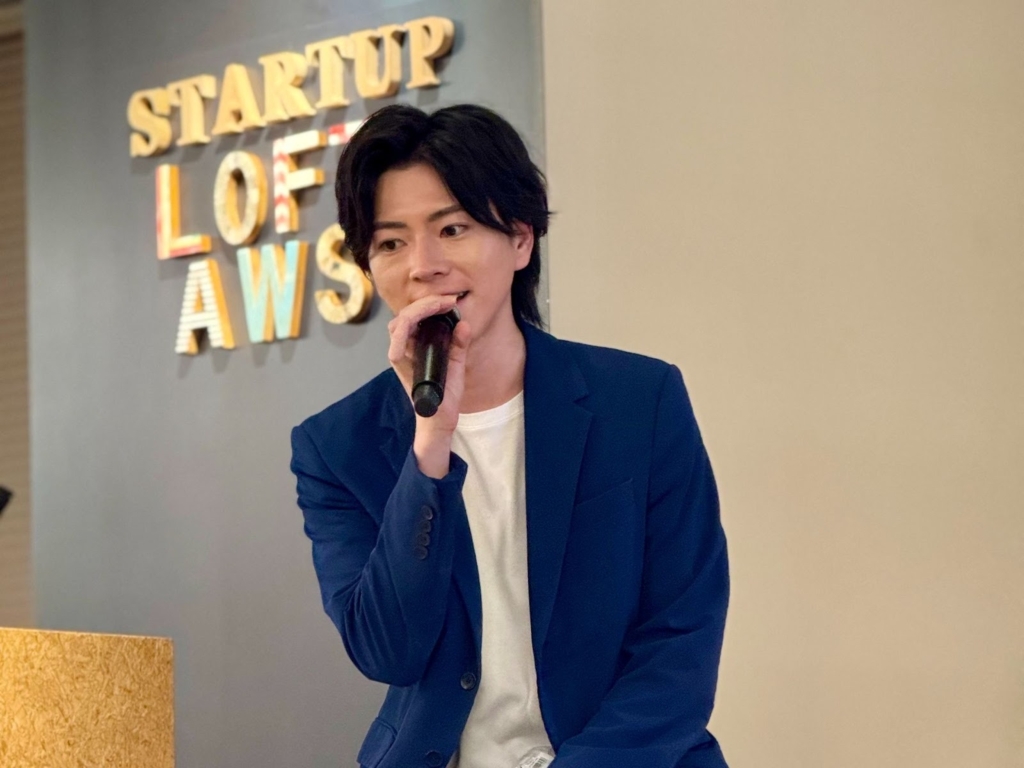
テーマ2:AIネイティブの台頭と“埋め込み型”の限界
小林:ARRが1年で1億ドル到達という、あのスピードで伸びる例はこれまでになかったですね。
橘さん:DevinやCursorのような、名前も知られていなかった若いプレイヤーが王者になっているのは象徴的です。一方で、既存のSaaS勢が勝てていないというのも現状の特徴です。埋め込み型はそれほど難易度が高いということでしょう。
小林:埋め込み型が難しい理由はどこにあると見ていますか。
橘さん:根本的にUXが違うからです。例えば、日本においては楽天ぐるなびが対話型AI「UMAME!」で伸び始めていますが、従来の検索ディレクトリ型(条件を入れて絞る前提)のサービスに対話型モジュールを後付けするのは非常にハードルが高いことです。
これはモバイルの歴史にも通じます。スマホ黎明期にはブラウザ上で動く擬似ネイティブアプリ(Webアプリ)が一時的に流行りましたが、最終的には純粋なネイティブアプリには敵いませんでした。AIにおいても同様で、体験設計そのものが根本的に異なるため「AIネイティブなUX」を新たに探る必要があります。対話型AIには、対話型のUXが不可欠だというのが第一のポイントです。
さらに、Yahoo!のようなディレクトリ型の検索から、対話や文脈理解を前提とした新しい検索体験への変化も進んでおり、インターネット業界のプレイヤーは皆すでにそこに張り始めています。一方で、消費者側ではまだその変化に気づいている人が少ない。このアービトラージにどう投資していくかが問われている段階だと考えています。
小林:既存プロダクトに“埋め込む”形でAIを連携する難しさについて、小笠原さんはどのように考えられていますか?
小笠原さん:どちらのアプローチにも意義はあると思います。ただ、既存の業務プロセスにAIを埋め込む形で改善を図る場合「既存業務を10倍良くする」のは簡単ではありません。一方で、AIを前提にゼロから設計する「AIネイティブ」なプロダクトであれば、10倍の改善や新しい体験を生み出す余地が大きいと考えています。DevinやCursorはその好例です。私たちも、ミーティングやスライド生成、営業、マーケティングといった領域をAIネイティブで統合することを目指しています。
ただ、大企業などでは既存のUIに慣れたユーザー様が多く、AIネイティブな操作体系に戸惑うケースも少なくありません。また、「人のほうが精度が高い」と考える方もまだ多くいらっしゃいます。業務フローを自ら構築・理解してきた方ほどAIをうまく使いこなせる一方で、これまでシステムに委ねてきた方は、AIネイティブな環境では迷いやすい傾向も見られます。
だからこそ私たちは、ユーザー様のリテラシーや現場環境に応じて、既存システムへの埋め込み型と、AIを前提としたネイティブ型の両方を提供する方針を取っています。
小林:ユーザーごとにAIの理解度やリテラシーが異なる中で画一的なプロダクトを一気に展開するのは難しいように思いますが、その点はいかがでしょうか。
小笠原さん:おっしゃる通りで、実際に両方のニーズがあります。Sales MarkerのUI上で使いたい企業様もいれば、Orcha(自社マルチAIエージェント)側のUIからSales Markerの機能を使いたい企業様もいます。今はまさに過渡期にあり、両輪で対応するのが最も現実的だと考えているので、どちらのUIでも使えるようにセットで提供しています。
小林:ありがとうございます。AI面接の領域ではどうでしょうか?
橘さん:アメリカや中国の動きを見ると、日本はやや遅れている面があります。アメリカではすでに単一のAI面接プラットフォームをみんなが利用するというフェーズが明確に来ているだけでなく、そうしたアプリケーションレイヤーのプレイヤーが何百億円規模で資金調達を行うなどSaaSの発展過程をAI SaaSでもなぞっている状況です。
ヨーロッパはAI Actという法律の影響で、産業の成長としてはほとんど停滞していると思っているので、その点、日本はまだ発展途上ではあるものの市場としては大きな可能性を秘めていると感じています。
ただ、“最前線の人たち”に限れば、日本とアメリカで大きなタイムラグはないとも感じますね。
小林:なるほど。現場で使う人たちに限れば、あまり違いはないわけですね。
橘さん:そうですね。むしろ大企業に関しては、日本のほうが進んでいる可能性もあります。マクロ的には日本の一般消費は遅れていると言われがちですが、大企業のAI予算は莫大ですよね。サービス提供者としての日本はまだ遅れていますが、導入側=消費者としてはアメリカ企業にとって非常に良い顧客になっているのが現状です。

テーマ3:日本発AIスタートアップの行方:ローカル戦略とグローバル競争
小林:ありがとうございます。少し話題が変わりますが、アメリカのトレンドを見ていると、ここ1〜2年はホリゾンタルなプレイヤーが伸びている印象です。2〜3年前は「AIは特化すべき」「データを取るべき」といった論調が主流でしたが、お2人はどう見ていますか?
橘さん:答えを断言するのは難しいですが、私はSaaSがたどった歴史の焼き直しがAI SaaSでも起きているという見立てです。SaaSの初期と同じく、まず“余白が大きい領域”に資金が集まり、ホリゾンタルなプレイヤーが市場を埋めていく。その後に、特定領域に深く入り込むバーティカルなプレイヤーが登場するという歴史の繰り返しになると考えています。
小笠原さん:おっしゃる通りで、まずは橘さんの言う通りホリゾンタルに広がっていくのが自然な流れだと思います。たとえばスライドひとつ取っても、コンシューマ向け・コンサル向け・事業会社向け、さらには社内向け・社外向けなど多様な用途があります。その中で、「コンサル向けのスライド」はコンサル経験がないと作れない部分が多く、私はコンサルとエンジニアの両方を経験してきたからこそ、現場で叩き込まれたノウハウを機能に落とし込むことができていると感じます。
そうした掛け算こそが今後日本で埋めるべきピースだと思っています。私たちはCrossBorder株式会社という社名で創業したのでグローバルで挑戦することが前提ですが、海外のホリゾンタル製品をそのまま日本に持ち込んでも実際の現場では意外とフィットしないケースが多い。一見競合しているようで、実際の提案先では比較対象にすらならないこともあります。こうした文脈理解の深さが、今後ローカルプレイヤーの強みになると考えています。
小林:なるほど。PeopleXでは、どんなローカル性にアプローチして戦っていくのでしょうか。
橘さん:HRは完全にローカルバリアが効く領域です。SaaS時代もそうでしたが、タレントマネジメントや採用媒体の領域では外資が苦戦してきました。新卒採用という独自の文化が存在する以上、この領域では日本発のプレイヤーが優位に立てます。私たちはこの文脈を踏まえながら、グローバルのスピードとローカル特性の両面を掛け合わせて戦っていくつもりです。
小林:少し話は変わりますが、アメリカのトレンドの文脈でお聞きします。ここ1年ほどの取り組みの中で、「ここはChatGPTや外資が来ても勝ちにくい」と感じた領域はありますか。
橘さん:Grokを見て確信したのですが、いわゆる“アニちゃん”系のAIキャラクター路線はまだ品質が低い。アニメ・漫画・キャラクターづくりは日本が負けてはいけない領域で、実際に強いです。私がシンガポールのAI面接系スタートアップにデモをした際にも「アメリカより進んでいる」と言われました。ゲームやアイドルのように「キャラと会話する」体験は日本が圧倒的に得意な分野です。
ただ、草の根レベルの挑戦は多い一方でマネタイズが難しい。一定のマーケティング費用とIP連携が鍵になります。このあたりはゲーム技術やゲーミフィケーションを得意とする日本の大手企業が動ける領域で、すでにいくつも仕込みが進んでいると思います。
小林:では次に、AIスタートアップとして「投資すべき領域」について伺います。どこにお金をかけるべきでしょうか。人材なのか、APIコストを支える資金力なのか——。
小笠原さん:重要なのはユースケースへの特化度だと考えています。日本ではSaaSよりもSI市場の方が依然として大きく、「どの業務にどう落とし込むか」に投資する価値があります。もう一つは、自分たちしか知らない真実——つまり独自のインサイトを持てるかどうかです。そこに資金を投じ、その仮説を具現化できる人材を採用すべきです。単に「作れる人」ではなく、「誰も作れていないものを作れる人」に投資する。それが競争優位につながると考えています。
橘さん:まさにおっしゃる通りで、いま日本ではそうした人材やプレイヤー自体がまだ少ないのが現状です。生成AI領域において、まだ大物スタートアップは出てきていないと思います。SaaSの上場企業群もAIネイティブSaaSを十分に出せていませんし、供給が追いついていない。若い起業家は出てきていますが、大企業向けの営業組織を持てていないケースが多い。一方で、上場企業側の新規事業も10人規模など小さなものが多い。今はスマホシフト以上の大波で、供給不足とチャンスが同時に来ているタイミングだと考えています。
小林:最後にAIの未来展望について伺います。今後2〜3年でどのような事業・会社を目指していかれる構想でしょうか?
小笠原さん:私たちはクライアント様の売上成長の実現をゴールに据えています。ターゲット選定からインテント検出、文面生成、アプローチ、商談獲得、分析、受注、さらにマーケティングや採用まで——成長ドライバーを一気通貫でオーケストレーションする。最終的には、「任せておけば事業が伸びる」状態をつくりたいと思っています。対面で顧客に向き合う以外の業務は、ほぼ自動化していく構想です。
小林:セールス起点に限らず、アップサイドを広く担うイメージですね。
小笠原さん:はい。事業のアップサイド全体を担う会社を目指しています。
橘さん:クラウドの時代には日本に15年のタイムラグがありましたが、LLMは2023年スタートで、その遅れはほぼありません。IaaSやモデルで勝負するのではなく、アプリケーションレイヤーで世界と戦うべきです。AI面接の分野では、すでに日本がアメリカを上回る部分もあります。今は世界に打って出る“ラストチャンス”です。AIトレンドは1〜2年でキャッチアップされるので、躊躇せず進むべきだと思います。
その背景には資本の流れもあります。アメリカのVCは出資に慎重になっており、逆に日本の大企業がLP出資を通じて存在感を強めています。日本企業にはまだ投資余力がある。スタートアップ側は、事業会社本体のマネーをどう取りにいくかが鍵だと考えています。
小笠原さん:加えて、日本は“ものづくり”が好きな国ですが、従来は実装リードタイムの長さとマーケティングの弱さが足かせになっていました。AIなら「考える→形にする」までが非常に短い。さらに、マーケティングの手段も大きく増えている。今のこのタイミングは逃してはいけないと私自身も思っています。
小林:ありがとうございます。まとめると、資金余力があるうえに、AIによって日本の“ものづくりの弱点”が補われつつある。日本から世界へ挑戦できる局面にあるということですね。本日はご登壇ありがとうございました!